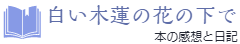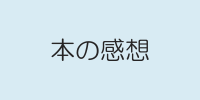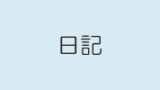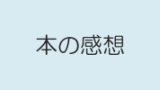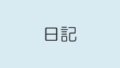『ザリガニの鳴くところ』は2021年本屋大賞、翻訳部門受賞作で映画化もされている。翻訳小説は得意じゃなくて滅多に読まない派なのだけど、映画化をキッカケに「面白い」との評判を聞いて「そんなに面白いなら読んでみるか」みたいな気持ちになって手に取った。
で…確かに面白かった。最近の世の中の問題や考え方の流れを上手いこと取り入れつつ、独特の世界感を楽しめる作品になっていた。たぶん…だけど梨木香歩の世界が好きな人は気に入るように思う。
ザリガニの鳴くところ
- ノースカロライナ州の湿地で男の死体が発見された。人々は「湿地の少女」と呼ばれているカイアに疑いの目を向ける。
- 主人公のカイアはわずか6歳で家族に見捨てられたったひとりで生きてきた。
- 学校にも通ったことのないカイアは読み書きが出来ず、読み書きを教えてくれた少年テイトに恋心を抱くのだが彼は大学進学のため彼女を置いて去ってしまう。以来、村の人々に「湿地の少女」と呼ばれ蔑まれながらも、湿地の生き物と共に静かに暮らしていた。
- しかしあるとき、村の裕福な青年チェイスが彼女に近づいて……
感想
凄く面白かったのだけど、この作品を「ミステリ小説」に分類するのは少し疑問を持ってしまう。殺人事件と裁判が軸になっているけれど謎解き要素はそんなに大事なところじゃない気がする。私はミステリマニアではないけれど、ミステリ小説としてのレベルは大したことない気がする。
「じゃあ、何が面白かったの?」って話。『ザリガニの鳴くところ』は面白いポイントが沢山あって、人によって刺さる部分が違うと思う。「これでもか!」ってほどに色々な要素を詰め込んでいて普通なら盛り過ぎて散漫な作品になってしまうところをギリギリのところで踏みとどまっている。
主人公のカイアはわずか6歳にして家族に取り残されてしまって、たった1人で湿地のほとりに建つ家で暮らしていく。
カイアは昭和の名作アニメ『ペリーヌ物語』のように知恵を絞り、どうにかこうにか生きていくのだけど、まぁ普通に考えると「それって…ネグレクトだよね?」って話。実際、役所の介入もあったのだけどカイヤは役所の突入をかわして1人で生きていく道を選ぶ。
ちなみなカイヤは1946年に生まれた設定なので、今を生きる高齢者達と同じ時代を生きている。「ちょっと昔の話」くらいの昔感なので時代背景はイメージしやすいと思う。
学校にも通わずたった1人で生活するカイヤを支えたの黒人のジャンピン&メイベル夫婦とテイト少年。テイト少年はカイヤに読み書きを教えてくれた。小説において「読み書きを教える」ってイベントは恋愛の鉄板。当然のようにカイヤはテイトに恋心を抱くようになる。
正直、黒人のジャンピン夫妻については「イイハナシダナー」ではあるものの、大人目線で読むと彼らの応援があったからこそ、カイヤは公共の保護を受けることができず社会から隔絶されて孤独を深めてしまった…って側面もある。カイヤを助けてくれたのが白人の知識人であったなら、もっと違う展開になっていたのではないだろうか。
カイヤの不幸は貧困だけでなでく、彼女と彼女に関わる人達の知識が不足していたから…ってところは現代にも通じるところで興味深い。
- ネグレクトされた少女
- 自然に寄り添って生きる生活
- 少年と少女の淡い恋
- 心優しい黒人夫妻と白人の少女の温かな関係
……この美しい物語の中に殺人事件をぶっこんでくるのなかなかの物だと思う。カイヤは容疑者として勾留され裁判の描写が延々と続く。「男を殺したのは誰なのか?」「そもそも男は本当に殺されたのか?」みたいな話になっていく。
今回はネタバレを避けたいので事件の真相については書かないけれど、正直私は真相については説得力に欠ける気がして評価できない。と言うのも私は物語の早い時点で真相に行き着いたのだけど、その後の展開を読んでいくうちに「あれ? 私の考えは間違ってたみたい」と思わされたのだ。「あの真相に行き着くのであれば途中の展開は何だったんだよ?」って気持ちでいっぱい。
「私の感動とか、それまでコツコツと積み上げてきたことはなんだったんだよ?」とオチを読んでガッカリしてしまった。それまでの展開が素晴らしかっただけに残念ではある。
……とは言うものの、それぞれのエピソードは魅力的で一気読み出来るくらいに面白い作品だった。
作者のディーリア・オーエンズは『ザリガニの鳴くところ』が処女小説とのことだけど、生物学者で何冊かの専門書を出版しているらしい。
『ザリガニの鳴くところ』は色々とツッコミどころの多い作品ではあるけれど、アメリカの自然の美しさや自然界の残酷さ、そしてアメリカ社会の問題点などを盛り込んで1つの物語になっている…ってだけでも称賛したいし、日本には無いタイプの小説なので興味がある方は読んでみて損はないと思う。