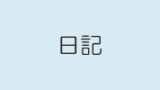古き良き東京の芸人さんの物語で、ちょっとイイ感じだった。
作者の荒木一郎は芸能人(私はよく知らない人だが)らしいので、一応タレント本系になるのだろうか。それにしても良かった。
関西人の私は、芸人というと関西人を連想してしまう。関東は落語家さんしかいないくらいの認識なのだ。
「関西人でない、お笑い芸人さんもたくさんいる」と知識で分かっていても、自分の中で「芸人=関西人」と言う図式はなかなか消えてくれないらしい。
後ろ向きのジョーカー
ピンク・レディーの「さよなら公演」が後楽園球場を満杯にしたその当日、新宿・歌舞伎町のライブハウス前では、ジョー小峰をひと目見ようと、小雨のなか長蛇の列が出来ていた。
昭和55年から始まった素人芸を全面に押し出す漫才ブーム。テレビに席巻されたお笑いの「55年体制」に逆らうように、鋭利なジョークを飛ばし続けた天才芸人の栄光と挫折。
長年の沈黙を破って荒木一郎が世に問う、待望の書下ろし小説。
アマゾンより引用
感想
「芸を磨いてこそ芸人」だとか「女遊びは芸人の肥やし」だとか、涙ぐましいほど古臭い感覚の主人公。
ちょっと定形通りなところはあるけれど、心優しいロマンチストな面も持ち合わせていて、なぜか憎めない感じ。
人を喰ったような態度も「芸人」だから許せるのだと思う。会社員で、ああいう人がいたら、嫌われ者間違いなしという勢いだ。
途中、なんども主人公が舞台で喋る漫談ネタが入るのだけど、それはちょっと詰まらなくて残念だった。
時事ネタが多かったのが原因だと思う。
お笑いって時代とともに流れていくものだから、どうしようもないのだけれど。
この作品とは関係ないが、面白いと言われる「横山やすし・西川きよし」の漫才だって、今になって観ると「へぇっ。面白いなぁ」とは思えても笑えないもの。
お笑いの世界って切ないよなぁ。
華やかさには欠けた作品だったし、上手い文章だとも思わなかったけれど、感じるところの多い作品だった。