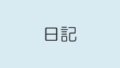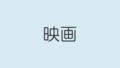私は読書が好き…と言っても、読んでいる大半は日本の小説。外国文学はそれほど多く触れていないのだけど、今まで読んだ外国文学の中ではパール・バック『大地』が1番好きだ。
初めて読んだ時は「どうしてアメリカ人のパール・バックが中国を舞台に生き生きとした小説が書けたのだろう?」と驚嘆したし「アメリカ人の感覚があったからこそ、あの作品が産まれたのかもな」とも思った。
まぁ、何にせよ私にとってパール・バックは「なんか…凄い作品を書いた外国人の小説家」って感じなのだけど、つい先日、パール・バックの娘が知的障がい者だったことを知った。
現在、私は医療型児童発達支援センターで障害児の保育を行っていて「これは読まねば(使命感)」みたいな気持ちになったので、すぐさま図書館でパール・バック関連の本を借りて読んでみた。
母よ嘆くなかれ 〈新訳版〉
- 〈いつまでも子どものままの〉娘と歩んだ母親・ノーベル賞作家パール・バックの手記。
- 娘の障害を受け入れることが出来るまでの苦悩や、娘が終の棲家として過ごせるための施設探しなどを赤裸々に綴る。
感想
パール・バックの生きた時代と現代とでは障がい者を取り巻く環境(教育や支援体制)が変わっているので『母よ嘆くなかれ 』で書かれている内容をスヘで肯定的に捉えることはできないけれど現代にも通じる部分が多くて驚いた。
- 娘が産まれた時の喜び
- 娘が障がい者かも知れないと疑いを持った母の不安
- 「治るかも知れない」との希望をかけての病院行脚
- 我が子の障がいを受けてれることが出来るまでの過程
- 子の終の棲家を探しての施設めぐり
どれもこれも「障がい者の子を思った親が通る道」としては、現代とあまり変わらない。そして『母よ嘆くなかれ』は障がい者を持った子の親の気持ちに寄り添った優しい言葉に溢れている。
『母よ嘆くなかれ』は「現代にも通じる読み物」としても優秀であるけれど「社会福祉の歴史」を知る上でも貴重な資料だと思う。
例えば…パール・バックが娘の障がいを受け入れて、娘の終の棲家となるべき施設を探していた時のエピーソード。
パール・バックは「コレジャナイ」とその施設は見学しかしなかったのだけど、当時のアメリカには「知的障がい者を持った上流階級の人間向け」の施設があった…って事実にビックリした。
その一方で、当然だけど貧困層で暮らす障がい者は支援を受ける…どころの状況ではない。「地獄の沙汰も金次第」ではないけれど、福祉政策が整っていないと当事者やその家族の苦労は半端ないことになってしまう。
今の日本も障がい者が暮らしやすい国だとは言わないけれど、少なくとも100年前よりはマシになってきている。それは「良くしていこう」と頑張ってきた人達の努力の結果なんだなぁ…と思うと感慨深いものがあった。
ちなみに。パール・バックはその後、混血児のための養護施設(昔で言うところの孤児院)を作ったりして福祉の世界に貢献している。日本人とも親交を深めていたとのこと。
知的障がい者の母としてのパール・バック、福祉事業者としてのパール・バックについてもっと知りたいな…と思ったので他の資料も探して読んでみたいと思う。