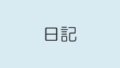キリスト教作家である三浦綾子が晩年に記したエッセイ集である。
他の著作同様、宗教色が濃い上に、エッセイとしては面白みに欠けるが、つれづれに書いた「日記」だと思えば、それなりに読めるかと思った。
どちらにせよ三浦綾子のファンでなければ読み辛いかなぁ……という印象は否めない。
明日をうたう
人間の生活は、つきつめれば誰しも感謝と謝罪の二語につきるのではないか―。日々襲いかかる病魔と闘い、一人遺言をしたためながら胸に浮かぶ、時、人、言葉…。作家デビュー以後の軌跡を刻む本書の執筆再開を願いながら、ついに叶うことなく七十七歳の生涯を終えた著者が最後に遺した、魂を揺さぶる感動の書。
アマゾンより引用
感想
三浦綾子は若い頃に結核と脊椎カリエスのため、長い闘病生活を送った人なのだが、それ以降も生涯に渡って病気と縁が切れなかったらしく、この作品は「闘病日記」の色合いが濃い。
とりわけ、自分を助けてくれる夫との生活に感謝するところが多く遺書めいた雰囲気があるだけに、面白くないながらも襟を正して読むことができた。
三浦綾子の作品は宗教色が濃い上に、やや説教臭いところがあり考え方としては素直に受け入れられない部分も多いのだが私自身は、こっそり好きだったりする。
たぶん作品の中の「ひたむきさ」に惹かれているのだと思う。
信仰生活、夫との生活、人と対峙して考えること……作品に取り組むひたむきな姿勢と、作中に生きる登場人物のひたむきさに、うっかり熱くなって読んでしまうような、そんな節がある。
この作品では、作者がそれまで書いた小説の登場人物のモデルが明かされていた。
三浦綾子は『塩狩峠』や『泥流地帯』の登場人物を夫の母親や、夫の兄をモデルにしていたと描いていて、作品を読んでいる読者なら「なるほど」と頷けることろがあると思う。
私など「なるほど」と思うことが多かったのだ。キラリと脇役が輝いていた理由は、身近な人物がモデルになっていたからか……と。
小説は作り事り世界であるけれど、どこか現実に根ざしたところがあると深みが出てくるのだろうなぁ……と思った。
上質なエッセイ集とは言えないまでも「楽屋話」として、あるいは「三浦綾子ファンブック」として読むのであればそれなりに楽しめる1冊だと思った。