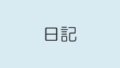私はここ数年、村田喜代子を推しているのだけど、今回の作品は正直言ってよく分からなかった。
名作だと思うし、力作だとも思う。だけど感覚的なところでついていけなかったのだ。
村田喜代子はどんどん進化していて、在りし日の河野多惠子を思わせる。「凄いんだけど実はよく分かんないな!」みたいな。
エリザベスの友達
認知症の母たちの目に映るのは、かつて彼女がいちばん輝いていた時代――。
いったいどこに帰っているのかしら? 長い人生だったでしょうから、どこでしょうね。
介護ホームに暮らす97歳の母・初音は結婚後、天津租界で過ごした若かりし日の記憶、幼い娘を連れた引き揚げ船での忘れがたい光景のなかに生きていた。
女たちの人生に清朝最後の皇帝・溥儀と妻・婉容が交錯し、戦中戦後の日本が浮かびあがる傑作長篇。
アマゾンより引用
感想
舞台は認知症の高齢者が暮らす介護施設。
88歳、95歳、97歳の老女とその家族の物語。認知症の高齢者が出てくると「はいはい。介護小説ね」と思ってしまうかも知れないけれど、この作品は介護小説ではない。
認知症の老女達にはそれぞれに生きてきた過去があり、主人公格の初音さんは若い頃は天津租界で暮らしていて、幼い娘を連れて引き揚げ船で帰国した過去がある。
老女達は昔の記憶と今の生活を行き来していて、その中で初音さんの記憶から清朝最後の皇帝・溥儀と妻・婉容が浮かび上がってくる。
認知症の高齢者が出てくる小説って、どうしても悲惨な話が多くなりがちなのだけど、この作品はまったく違う。
ふわふわと過去と現在を行き来している老女達は、いまを生きている人でありながら、異世界人のような感じがして掴みどころがない。「認知症になって気の毒になぁ」と言うよりも、むしろ「こういう老後もありなのかもね」みたいな気持ちになってしまった。
天津租界から引き揚げいきた初音さん以外にも、妊娠しやすい体質で沢山の子どもを産んだ乙女さんや農家で育ち、初恋の人を戦争で亡くした牛枝さんなど、作品に登場する老女達はそれぞれ懸命に生きてきた過去があり、現在は認知症患者として過去と現在を行ったり来たりしている。
現在パートの描写はなかなかリアリティがある
認知症の親の様子を見に来る子ども達と認知症の噛み合わないやり取りや施設での生活の様子などは若い作家さんが描くのは難しいのではないかと思った。
ただ、リアリティがあり過ぎて、初音さん達の世界へ向かいつつある母達と向き合っている私は読んでいてイライラしてしまった。要するにそれくらい上手いって事だ。
作品の出来としては素晴らしいとは思うものの、過去と現在を行き来する老女達についていけず、心から楽しんで読む事が出来なかった。
ただ「夢と現実を行き来する」とか「過去と現在を行き来する」のは村田喜代子が得意とする手法で、例えば『屋根屋』でも夢と現実を行き来するのがテーマになっている。
村田喜代子は2018年現在、御年73歳。この年齢でこんなにコッテリした作品を生み出すのだから恐れ入る。
今回の作品は個人的には楽しめなかったけれど、次回の作品も楽しみにしている。