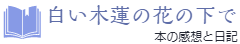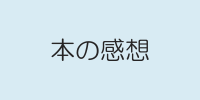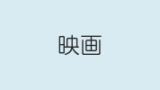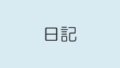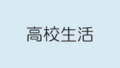『ハンチバック』は第169回芥川賞を受賞作。作者の市川沙央は人工呼吸器をと電動車椅子を利用する重度障害者。
この感想をアップする2023年7月現在では紙媒体での単行本は発売されていないのだけど、KindleとAudibleで紙媒体に先駆けて公開されてる。私はAudible版で耳から聞いた。
慌てなくても8月になれば単行本が発売されるのだけど「一刻も早く読みたい」と言う場合はAudibleで聞いてみるのもアリだと思う(無料お試し期間だけ利用してAudibleが使い難い場合は解約しても良いかと)
芥川賞受賞作が電子書籍やAudibleで紙媒体の本より先に発表されるなんて凄い時代だな…って思うのだけど『ハンチバック』は作中で「障害者が紙の本を読む難しさと辛さ」について触れているので、作者の気持ちに沿った発売の流れなのかな…と思ったりする。
ハンチバック
- 主人公の井沢釈華は背骨がS字にゆがむ重度障害者で人工呼吸器がユーザー。両親が自分のために残してくれたグループホーム生活してい。
- 釈華は有名私大の通信課程でオンラインの授業を受けたり、コタツ記事(取材せずにネット上の情報だけで書ける記事)を書いたりして日々を過ごしているがお金には困っておらず、文章を書いて得たお金は寄付している。
- 釈華はヘルパーの介助無しでは生活出来ず、両親の配慮により入浴介護は必ず同性のヘルパーが付き添うようにしていた。しかしコロナ禍の中、どうしても人員調整がうまくいかず、釈華の了承のもと男性ヘルパーの田中が来ることになった。
- 入浴介護は何事もなく終わったが、その後、急に田中から釈華が運用しているTwitterの話題をされる。田中は釈華のTwitterアカウントを特定していたのだ。釈華の妊娠と中絶への興味を知った田中は……
感想
第169回芥川賞を受賞作の『ハンチバック』は「作者が人工呼吸器&電動車椅子ユーザーの重度障害者」と聞いて「一刻も早く読まねば」と言う気持ちになってしまった。
2023年7月現在、私は医療型児童発達支援センターと言う施設で働いていて、障害を持ったお子さん達の療育に携わっている。作者と同じような医療的ケアが必要なお子さんも多く「重度障害を持った女性の書いた小説って、どんな感じなんだろう?」と猛烈に興味を持ってしまったのだ。
『ハンチバック』は自分の仕事や関わっているお子さん達と重ねる部分が多くて今はまだ自分の頭の中で感想がまとまっていない状態なのだけど、ひとまず感じたことや考えたことをザックリ記しておきたい。
ちなみに。タイトルの「ハッチバック」とは「せむし」のこと。作中は自分の事を何度も「せむし(ハンチバック)の怪物」と表現している。
少しずつ身体が湾曲していく症状は作者や『ハンチバック』の主人公だけでなく、身体に障害を持った人には多くみられ私が関わっているお子さん達も「将来、出来るだけ身体の湾曲が進まないように」と日々、リハビリに励んでいる。身体障害のある方の中には障害の度合いが進んでいく事は多々ある現象。
『ハンチバック』つにいては感じたところが多過ぎて今のところ考えがまとまり切っていないのだけど、とりあえず「人工呼吸器を付けている人の生活の大変さ」とか「身体的な障害がある人の暮らしている世界」を知るだけでも読む価値はあると思う。
「それ」を知っている人達だと人工呼吸器の扱いとか痰の吸引の大変さについては「ああ…そうそう。そうですよね。めちゃ分かります」くらいの話だけど「それ」に触れたことの無い人達にとっては「今まで知らなかった世界」ではないかと思う。
また作中で主人公の釈華が「紙の本を賛否する人達の傲慢」について触れているところについては全ての人に知って欲しいと思わずにはいられなかった。
私自身はある一定の時期まで紙の本至上主義だったのだけど、老眼が進んで今までのような読書が難しくなってきてからは「世の中の本が全て耳から聞けたら良いのに」と思うようになっている。紙の本の良さは知っているし、紙の本でしか得られない感覚があることも承知しているけれど「紙の本が読めないのならAudibleがあるじゃない」くらいの気持ちになっている。
『ハンチバック』は障害者(マイノリティ)の生き辛さを描いた作品であると同時に格差社会にも焦点を当てているところが面白いと思った。釈華は障害者であるものの、資産家の娘で生活には全く困っておらず「自分が死んだら遺産は国庫に納められる」と言うところを語っている。
その一方、釈華をケアするヘルパー達は底辺層と言っても良いと思う。特に男性ヘルパーの田中は障害者でありながら、使い切れない資産を持っている釈華に対して悪意を含む感情を持って接している。
ヘルパーの田中については「プロ意識低いのでは?」とか「そんな事を言ったって仕方ないでしょ?」みたいに思ったりもするけれど、自分が田中の立場だったとして「釈華に対して嫉妬せずにいられるか?」と考えると、難しいかもな…とも思う。
障害を持った人は障害を持っていない人に嫉妬するし、お金を持っていない人はお金を持っている人に嫉妬する…なんだか有吉佐和子の『非色』の世界観と似ている気がした(『非色』の場合は人種差別だったけど)
さて。『ハンチバック』から「障害者云々…と言った要素を省いてしまうと、どうなるのか?」と言うとですね。これが意外とエロいと言うか下衆いと言うか。予想外にエッチな文章が多いので嫌いな人は嫌いだと思う。そもそも作品ののっけから「えっ?これってエロ小説なの?」って書き出し。「障害者だって性欲はあるんだぞ」的な話でもある。
ただし障害者の性欲云々…の部分が上手く昇華出来ていたかと言うと、そこのところは微妙だった。これについて作者自身の性体験による物かも知れないけれど「推理小説作家は人を殺さなくても人殺しが書ける」と言う考えからすると、稚拙だし表現も流れもテンプレでしかなく大雑把過ぎる。
後半の釈華と田中の関係などは曖昧な感じで終わっているし、何よりもラストがちっょと微妙過ぎた。「あえて」そうしたのかも知れないけれど、読んでいる側からすると「おいおい。そこ、ちゃんと書いてよ」と思ってしまう。
『ハンチバック』を文学作品としてみると、正直なところ荒っぽくて未完成品のように思えてしまう。だけど勢いとインパクトは半端ない。作者が言いたい事は伝わってくるし熱量の多さは理解できた。
『ハンチバック』が芥川賞に相応しい出来栄えなのかどうかは分からないけれど、衝撃的な作品であることに間違いないし次回作に期待したい。作者の手から同じような熱量でもって新しい作品が出てくることを願う。