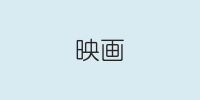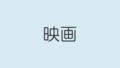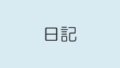『鉄道員』と言うと、浅田次郎原作で高倉健が主演した『鉄道員(ぽっぽや)』をイメージする人が多いと思うのだけど、私が観た『鉄道員』は1956年にイタリアで作られた作品。
主人公はイタリアで30年以上、鉄道一筋に生きてきたアンドレア。アンドレアとその家族を描いている。白黒作品なので「古臭いんじゃないかな?」と思っていたけど、いまでも充分に通用する名作だった。
鉄道員
あらすじ
鉄道機関士アンドレアは鉄道一筋に生きてきた愚直な男。幼い末っ子サンドロはそんな父親を誇りに思っていたが、長男マルチェロや長女ジュリアは父の厳格な性格を嫌っていた。
ある日、アンドレアの運転する列車に若者が投身自殺をする。しかもアンドレアは、そのショックにより赤信号を見すごし、列車の衝突事故を起こしかけ、左遷されてしまう。
アンドレアは、ストライキを計画中だった労働組合に不満を訴えるが、とり上げられることはなく、酒に溺れ始める。その頃、流産し夫婦仲が悪くなっていたジュリアの不倫が原因でマルチェロは父と口論となり家を出ていく。
職場ではストライキが決行されたが、アンドレアは機関車を運転し、スト破りを決行。仲間を裏切った形になってしまったアンドレアは友人達からも孤立し、家にも帰らなくなってしまう。
末っ子サンドロは酒場をめぐって父を探し出し、以前に父が友人たちとギターを弾いて歌った酒場に連れ出す。
旧友たちは再びアンドレアを温かく迎え入れ、家族との和解の兆しも見えてくる。
しかし、すでにアンドレアは身体を壊していて、家族や友人たちとの幸せなクリスマスパーティを終えた夜にベッドでギターを弾きながら息をひきとる。
向田邦子的あるいは橋田壽賀子的
『鉄道員』を観ている最中、ずっと「なんだか懐かしい感じがするんだよねぇ」と思っていた。そして後になって気がついた。『鉄道員』は日本でも一時期よくあった古き良きご家族ドラマそのものなのだ。向田邦子的と言うか、橋田壽賀子的と言うか。
アンドレアの家族は恐らくイタリアにある平凡な一家なのだと思う。お金持ちでもなければ貧乏過ぎることもない。アンドレアにしても、妻や子ども達ににしても、それぞれに良いところがあるけれど悪いところだってある。一つ屋根の下に暮らしてればギスギスすることもあれば、気持ちがすれ違うこともある。
それでも、それぞれ折り合いをつけて家族としてやっている…みたいなコンセプト。
日本も昔はこの類のドラマや映画が多かった気がするけれど、最近はとんと見掛けなくなった。だからこそ私は『鉄道員』を観て懐かしさを嗅ぎ取ってしまったのだと思う。
美人過ぎる美人女優
『鉄道員』を観て感心したのは、主人公アンドレアの長女、ジュリアを演じたシルヴァ・コシナが美人過ぎる…ってこと。日本人の女優さんに例えるなら吉永小百合クラス。
あまりにも綺麗なので作品を観終わった後で検索してしまったほどだ。
ジュリアを演じたシルヴァ・コシナはクロアチア(旧ユーゴスラビア王国)出身の女優さん。最初から女優を目指していた訳ではなくて、自転車レースの優勝者に花束を渡す役を務した時に、あまりにも美人だったからスカウトされて映画の世界に入ったとのこと。分かる…スカウトしちゃうの分かる。だって美人なんだもん。
とりあえずシルヴァ・コシナの美貌を堪能するためだけでも観る価値はあると思う。
イタリアの鈴木福
シルヴァ・コシナの美貌も凄かったけれど、末っ子のサンドロを演じたエドアルド・ネヴォラの可愛らしさも強烈だった。鈴木福もビックリの可愛らしさ。西洋の子役も素晴らしいなぁ!
サンドロは3兄弟の末っ子だけど、兄弟と言っても上2人とは年齢が離れ過ぎていて、両親からも兄弟からも甘やかされて育った甘々の男の子。「愛されるために生まれてきました」みたいな雰囲気があって「あ~。こう言うポジションの子っているよねぇ」と感心してしまった。
思うに…愛されまくって育った子は可愛い。(異論は認める)
私は作品が公開された時代を知らないけれど、大ヒットしたんだろうな…ってことは容易に想像出来る。「動物と子どもが活躍する映画は強い」と言うけれど、まさにそれ。しかも美女までついてくる。当時のイタリア人はさぞや熱狂したことだろう。
風俗の違いを楽しむ
さて。最初に「懐かしい感じがした」と書いたけれど、流石に日本とイタリアは違う訳で、物の考え方は日本のそれと随分違う。
なんだかんだ言ってアンドレアはイタリア男なので、妻とラブラブな描写があったり、イタリア人男性はマンマ・ミーアなので、成人した長男が母親に抱きついて甘える場面があったりして「やはりイタリアは日本人と違う…」ってところを見せつけてくれた。
今とは随分と時代が違うのでアルコールやタバコに対する考え方が違うのも面白かった。今の常識からだとアウトな部分も多々あるけれど、そこのところは「当時はこんな感じだったんだね」くらいのおおらかな気持ちで観て戴きたい。
たまには古い映画を観てみるのも悪くないと感じた名作だった。