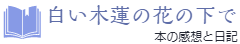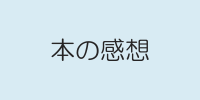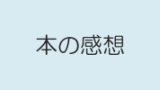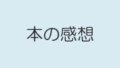正岡子規の研究家である著者が子規の俳句を通して書いたエッセイ集。
子規好きが読んでも面白いと思うが、漱石好きが読んでも面白いと思う。そして食べる事が好きな人が読んでも面白いだろうと思う1冊。
子規のココア・漱石のカステラ
「三月の甘納豆のうふふふふ」で知られる俳人・坪内ネンテン、初のエッセイ集。
正岡子規も夏目漱石も、甘いものが大好きだった…。子規と漱石の交遊や生活のエピソードにからめて、四季折々の暮らしを綴った、俳人・ネンテン先生の心温まる初のエッセイ集。
アマゾンより引用
感想
私は正岡子規の俳句が大好きだ。
ただ、正岡子規と言うと国語の教科書に載っていた、思いつめたような横顔の写真が印象的なのと結核を患って早世した俳人ということで、ストイックなイメージが強い。
いくら「正岡子規は以外と茶目っ気のある人物だった」という文章を読んでも泣いて血を吐いたり、今年ばかりの春が行くのを1人でかみ締めていたりする幸薄そうな人という印象を拭えずにいたのだが、この本を読んで、それが変わった。
よくよく考えてみれぱ正岡子規は「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺」を詠んだ人だったのだ。
柿が好きで、甘いものが好きで、日記に毎日食べたものを書き連ねるくらい食べること好きで。正岡子規は病気ではあったが、食べて、書いて、読んで……生きることをた楽しんでいたのだと思う。
ストイックどころか、親友にお金を借りて旅行しても飄々としていたりなんかして孤独を噛み締めるような俳句を読む反面、人好きだった正岡子規。私はますます子規が好きになってしまった。
この作品のエピソードで、いっとう気に入ったのは子規は「家庭団欒」というものを重要視していたってこと。
母と妹に「団欒」をすすめるものの団欒に付き合ってもらえるのは最初だけで、気に入ってもらえなかったという話。なんとなく状況が想像できて、笑えてしまった。
息子(兄)の気持ちは分かるが、母や妹は、そうそうノンビリしていられない。
食事の後片付けはどうする? 洗濯はどうする? 兄の好きな菓子パンは誰が買いに行く?「こまった子だねぇ」なんて思いながら、最初だけ「団欒」に参加するもののバタバタと、それぞれの仕事に戻っていったのだろうなぁ。
なんとなく彼の孤独よりも「さびしん坊・甘えん坊」の長男という側面を見たように思う。そして彼は「我が家の女どもは団欒を分かっちゃいない」ってなことを書いていたようだ。
あらためて子規の句集を読んだなら違った風に読めるだろと思う。
正岡子規の俳句を楽しむとき、正岡子規の人となりを知らなくても充分楽しめるのも事実だが、それらを知っていれば2倍楽しめるような気がする。
この本に出逢えて良かったと、心から思える1冊だった。