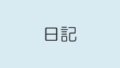蓮見恭子は初挑戦の作家さん。「母だけが知る、家族の秘密」と書かれた帯のキャッチコピーは最高だったと思う。
この作品ハッキリ言ってそれほど面白くなかった。
しかし帯は素晴らしかった…と言うか、帯が1番面白かったと言っても過言ではない。映画で言うところの「予告編が1番面白かったね」と言うアレと同じ。
始まりの家
銀座で美容院を経営する一家の物語。本の帯には「子ども頃の病気が原因で子どもを産むことが出来ない末娘が自分の母に代理母を頼む話」と言うふうに書かれていた。
「なるほど…代理母とか不妊症の問題か…」と読んだ訳だけど、なんだか全く思ってたのと違う展開だった。
不妊症云々…の話があるのは事実だけれど、代理母なんてのは物語の主軸でもなんでもなかった。実際は「銀座で生きてきた堅気の家族の物語」ってところ。
子どもを産むことの出来ない末娘にまつわる秘密が物語の核になるのだけれど、なんと言うかこう「いらない登場人物、多過ぎじゃないの?と言う印象を受けた。
話の筋自体はそれなりに面白いのだけれど、全体的にまとまっていないように思った。
代理母の話でもなく、家族の歴史(秘密)の話でもなく、強いて言えば「銀座で生きてきた美容院一家の物語」ってところだと思う。
家族の要となる母親は腕の良かった夫を亡くしてから、夫の残した美容院を切り盛りしている。5人の子ども達はそれぞれ独立していて、テレビドラマで言うところの『渡る世間は鬼ばかり』と同じ方式。
『渡る世間は鬼ばかり』と大きく違うのは、5人も子どもがいるけれど、5人全員が物語に関わる訳じゃないってことだ。
最近は絶滅してしまった「昼ドラ」で映像化すれば、そりなりの物になると思うのだけど、1冊の本に詰め込むような話ではないと思った。
作者は横溝正史ミステリ大賞の優秀賞を受賞しているそうなので、もしかたら本当はミステリ寄りの人なのかも知れない。
ミステリなら多少登場人物が多くて、空気でしかない人がいるのもアリかも知れないけれど、一般的な小説だと違和感があり過ぎて戴けない。
一応、良い感じのハッピーエンドにまとまっているし「みんないい人だった」みたいなオチがついているけれど、最後まで読んでもモヤッっと感が半端ない。
「小説には構成力が大切なんだな」ってことを考えさせられた作品だった。