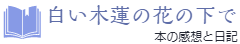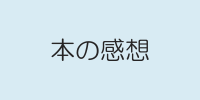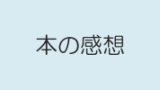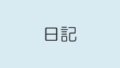『宙わたる教室』は大阪府立高校定時制の科学部が日本地球惑星科学連合大会で優秀賞を受賞した実話をベースに書かれた青春小説。第70回青少年読書感想文全国コンクール課題図書になっていてNHKでドラマ化もされていたらしい。
話題になっていたのは知りつつも読まずに放置していたところ、Audible化されたので読んで(聞いて)みることにした。
宙わたる教室
- 定時制高校が舞台の青春小説。
- 定時制高校に通う生徒達はそれぞれ個性的。21歳の岳人は負のスパイラルから抜け出せずゴミ処理業者として働いている。アンジェラは子ども時代に学校に通えなかった過去を持つ。佳純は起立性調節障害で不登校となり定時制に進学。70代の長嶺は、中学卒業後すぐに集団就職で上京た過去を持つ。
- 「もう一度学校に通いたい」という思いで集まった彼らは理科教師・藤竹叶を迎え、科学部を結成します。
- 藤竹の指導のもと彼らは学会での発表を目指し、「火星のクレーター」を再現する実験に挑戦しするのだが…
感想
少し前に読んだ『死んだ山田と教室』の時も感じたけれど、最近は「現代の若者の生き辛さ」みたいなところを書くのがトレンドなんだろうか?『宙わたる教室』は「定時制高校の科学部が日本地球惑星科学連合大会で優秀賞を受賞する青春小説」であると同時に現代の若者の生きづらさを明らかにした作品だと感じた。
実際にあった科学部がどういう編成だったのかは知らないけれけど『宙わたる教室』の科学部のメンバーに外国にルーツを持つ生徒がいたり70代の生徒がいたり、元不登校の生徒がいたりするところに設定の巧みがある。
実際、昔の定時制高校と今の定時制高校では生徒の層が変わってきているらしい。昔は「進学したかったけれど家が貧しくて進学できなかった人」が多かったと聞くけれど、最近では不登校の子どもや外国にルーツを持つ人が多いそうだ。
70代の男性を入れてきたのは「今の子ども達は恵まれていると言われるけれど、誰も彼もが貧乏だった時代よりもある意味生き難い社会で暮らしている」ってところを表現するためだったのだろうな…と思う。
昔より豊かな時代に生まれたからと言って昔より幸せとは限らない…ってところは私も我が子やその周囲を見ていて感じるところがある。社会格差による教育格差があったり、いじめや不登校の状況も年々酷くなる一方。
『宙わたる教室』の登場人物達はそれぞれに「難アリ」で、そんな集団が大きな目標に向かって進んでいく…というのは青春小説のテンプレ。最初から最後まで安心して読むことができた。
理科教師の藤竹叶があまりにもチートキャラ過ぎるところが少し鼻についたけれど、それについても「小説だしアリか」と許容範囲内。全体を通してよく出来た作品だと感心したし、青春小説としての質も高いくて青少年読書感想文全国コンクール課題図書になったのも納得できる。
作者の伊与原新は『藍を継ぐ海』で直木賞を受賞とのこと。私はまだ読んでいないので、是非読んでみたいと思う。