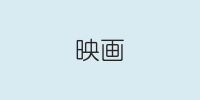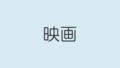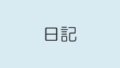『ビリー・リンの永遠の1日』は2016年に公開されたアメリカ映画。原作本は新潮クレスト・ブックスが発売されているが日本でも公開される予定だったが未公開のまま現在に至る。
ケーブルテレビでなんとなく録画して視聴したのだけど、予想外に面白くなかった。
一応、戦争映画のくくりに入ると思うのだけど戦闘シーンはほとんどなくて、どちらかと言うと社会派映画に近い作り。
今回の感想は軽くネタバレを含むのでネタバレNGの方はご遠慮ください。
ビリー・リンの永遠の1日
あらすじ
2004年、イラク戦争に出征していた19歳の青年ビリー・リンは、味方を助けるために銃撃戦の中へ身を投じる姿を偶然ニュースに取りあげられて、一躍英雄となる。
一時帰国したビリーはブラボー隊の仲間と共に全米各地を巡る凱旋ツアーへと駆り出される。
凱旋ツアーの中で、ビリーはイラクへ戻るのをためらう気持ちが芽生えると同時に、自分が英雄として扱われることに違和感を抱き始める。
そもそもビリーは愛国心から志願して兵士になったのではなかった。
ビリーと仲の良い2番目の姉のキャスリンは、運転中にスピンした車に激突され、顔を63針縫う大怪我を負い、当時の婚約者から婚約破棄される。
ピリーはキャスリンを見捨てた男の車をボコボコにして、さらにバールを持って追いかけ回したことにより告訴されそうになるビリーは訴追を免れる代わりに入隊し、イラクに送られたに過ぎず、愛国者でもなければ戦争が好きじゃないのだ。
戦地へ戻る前日、凱旋ツアー最大の目玉としてアメリカン・フットボールのハーフタイム・イベントに招かれたビリーは、その大歓声の中で現実と戦争の記憶が交差する感覚に陥る。
戦争に行く若者のリアル
アメリカの戦争映画を観ていると、愛国心に溢れた若者が出てきたり、そうでなければ「本質的に戦争が好き」みたいなクレイジー野郎が出てくることが多いのだけど『ビリー・リンの永遠の1日』に登場する若者達はそうじゃなかった。
ビリーは姉を思ってのこと…とは言うものの、自分のしでかしたことが原因で軍隊に入らざるを得なかったし、ビリーの仲間達も似たり寄ったり。
ビリー達の凱旋ツアーの途中で、ビリーにタバコみたいな麻薬(コカイン?)をすすめながら、軍隊について質問してきた黒人男性も最初養うためにお金が必要だから軍隊に入りたいと言っていた。
『愛と青春の旅だち』とか『トップガン』等の空軍エリートを描いた作品と違って「戦争しか行き場がない」若者達の現状にスポットが当てられていたところが心に響いた。
人の心を掴む上官
ビリーが英雄と呼ばれるようになったのは、命懸けで上官を救おうとしているとこを報道されたのがキッカケなのだけど、その上官は部下たちに常々「愛している」と言っている。
またナンバー2の上官はビリーに対して何度となく「お前が必要なんだ。使えない仲間を頼むぞ」と言う言葉を繰り返している。
「愛している」「必要なんだ」と言われ続けた若者達が上官についていく気持ちは分かる気がした。
軍隊しか行き場のなかった若者が、誰かから愛され、必要とされたら「それりゃ身も心も捧げようって気持ちになるよね?」って話。
ビリーに対して「愛している」「必要なんだ」と繰り返した2人の上官は決してビリーだけにその言葉を言って訳じゃない。部下達全員に同じことを言っていた訳だけど、それまでの人生で他人から愛されたり、必要とされたら「頑張ります!」みたいな気持ちになるのは当たり前だと思う。
有能な上司って凄い(怖い)よなぁ。
ただ、この手法。軍隊しか行き場のなかった若者に効果てきめんだったけれど、褒められまくって生きてきたエリート相手だとどうなるのかは分からない。
英雄になっても必要とされていない人達
ビリーとブラボー隊の仲間達は全米各地で英雄として歓待を受ける。ビリーに至ってはアメリカン・フットボールのハーフタイム・イベントで知り合ったチアリーダーと良い感じになったりもする。
誰もがビリー達を英雄だと称賛するのだけど、ビリー達は行く先々で自分達が本質的には歓迎されておらず、誰からも必要とされていないことを感じる。実際、ビリーと良い感じになったチアリーダーの女の子もビリーを必要としていたのではなく「戦争の英雄と恋に堕ちる」ことに夢中になっていただけだった。
「自分達のいるべき場所は戦場しかない」と再び戦場に旅立っていくラストはあまりにも切ない。
『ビリー・リンの永遠の1日』は派手な戦闘シーンも無ければ、涙無しでは観られない感動の展開もなかったけれど、戦争について考えさせられる素晴らしい作品だった。