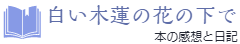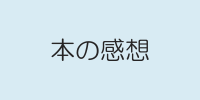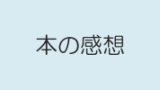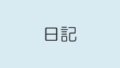『九年前の祈り』は第152回芥川賞受賞作。小野正嗣の作品を読むのはデビュー作の『水に埋もれる墓』以来。
なんとなく手に取らないままでいたけれど、主人公がシングルマザーだと知って「じゃあ読んでみうよかな」って気持ちになった。
だけど私は忘れていたのだ。小野正嗣ののデビュー作を読んだ時に「生理的に無理」って思っていた…ってことを。読まなきゃ良かった…。
九年前の祈り
- 第152回芥川賞受賞作の表題作を含む4つの短編からなる。
- 表題作『九年前の祈り』は三十五歳のシングルマザー「さなえ」がカナダ人の夫との間に授かった子どもと共に故郷戻って来る。
- さなえは希敏の突発的な行動に悩む中、九年前にカナダ旅行した「みっちゃん姉」の言葉を思い出し、心の奥が揺れる。
感想
最初に謝っておきます。小野正嗣作品、私には無理でした。文学的な価値云々の判断はさておき「人として無理」って感じ。もう作品から滲み出る空気感が無理。なので今回は全力的にdisった感想になるので、ファンの方は読まない方が良いかも知れません。あくまでも私の備忘録です。
この本は表題作を含む4作品が収録されているけれど、今回は表題作である『九年前の祈り』(芥川賞受賞作)のみの感想。ちなみに収録作の『悪の花』もノーサンキューだった。
『九年前の祈り』の中では何度となく同じ表現で主人公の息子のことが語られる。
引きちぎられたミミズのようにのたうちまわり大騒ぎする息子
この意味。どれだけの読者が理解しているのかな? 当事者家族なら「…あっ」ってなると思うのだけど知らない人は訳わかないし意味不明だと思う。作中でふんわり説明されているけれど、たぶんアレでは分からないだろう。
私は仕事でそういうお子さんと関わっているので「…あっ」ってなっちゃったんだけど、「個性的な子」でもなければ「親の躾」とか「環境の問題」でもなくて、明らかに発達障害。作者は発達障害をよく理解していて、そうだと分かるように書いているけれど分からない人には分からないと思う。
そして「みっちゃん姉」の息子は境界知能なのだと思う。いわゆる『ケーキの切れない非行少年たち』で登場するような「知的障害の枠から微妙に外れるけど一般社会で生きていにしてはシンドイ人」だ。
この作品は読む前になんとなくのあらすじを知っていた。「主人公はシングルマザーで年長の女性と心を交流させる話」だと。そりゃあ、心が通いますわな。だって周囲に似た状況の人間がいないのだから。
読んでいて全く希望が持てない作品だった。人の心の中を突き詰めるためのアイテムとして障害児者を使うのは手っ取り早いのかも知れないけれど「だったらキッチリとその世界を書き切れよ。雰囲気だけなぞってるんじゃねぇよ」って思ってしまった。
どうやら小野正嗣は障害者やマイノリティに目を向けた作品が他にもあるらしく「困難を抱えてつらい思いをしている人」に目が向いていることには間違いないのだけど、なんかちょっとコレジャナイ…と言うか。話のネタにしてほしくない…と言うか。そもそも引きちぎられたミミズ」なんて表現をぶっこんでくるあたり、なかなか残酷だよね…と言うか。
作者はデビュー作の『水に埋もれる墓』でも女性の性について気持ち悪い書き方をしていたけれど『九年前の祈り』の中でも母親の捉え方も気持ち悪い。描き方なんて千差万別で良いじゃない…って話なのだけど「女性でも母親でもないお前がなんで上から目線で分かった風に語ってるんだい?」みたいな気持ちになってしまったのだ。
それはそれとして。発達障害(知的障害)の強度行動障害の対応が難しいのはよく分かる。それこそ「引きちぎられたミミズのようにのたうちまわり大騒ぎする」はよくある話だし、実際はそれ以上に大変。
うっかり手にとって読んでしまったのだけど、これは不幸な事故だったと思っている。小野正嗣の作品はもう2度と読まないと心に誓った。