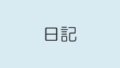『ともぐい』は第170回直木賞受賞作。河﨑明子は一時期「マイ推し作家」として追いかけていたけれど、最近の作品はさほど好きじゃなかったので「そのうち読もう」くらいのノリで今まで読まずにいたけれど、図書館でふと目に止まったので手に取ってみた。
そっか~。この作品で直木賞か~。
今に始まったことではないけど、直木賞ってあげるタイミング間違ってないか? 作家として脂がノリノリの時にあげずに「えっ? なんでこの作品? どうせなら◯◯で取らせてあげれば良かったのに」と思うことが多過ぎる。
『ともぐい』もホントそれ案件。悪くはないんだけど直木賞かと言うと微妙な気がした。
ともぐい
- 物語の舞台は明治後期の北海道。熊爪は山で猟師…というより獣そのものの嗅覚で、犬だけを相棒として獲物と対峙していた。
- ある日、穴持たずの熊が熊爪の領域に侵入してくる。熊爪は穴持たず熊の捕獲を依頼されるのだが、穴持たず熊よりも凶暴な赤毛の熊と対決することになる。
感想
「新しい熊文学の誕生」との触れ込みだったので、てっきり熊撃ち猟師の物語かと思っていたら、全然違った。
そもそも。北海道で羆をテーマにした作品は名作が多い。個人的には吉村昭の『羆嵐』が最高峰だと思っているけど、羆をテーマにした作品はワンサカある。志茂田景樹『黄色い牙』とか熊谷達也『漂泊の牙』とか。
ワンサカある熊文学(羆文学)のテーマはあくまでも「羆と人間の対決」だけど『ともぐい』のテーマは違う気がした。確かに主人公は猟師で羆と戦う場面があるけど、あれを熊文学と定義しても良いんだろうか?
……実のところ。物語の途中までは夢中になって読んでいた。北海道の山の様子や動物の匂いまで感じさせてくれて臨場感抜群だったし、熊爪のキャラクターも野性味と男臭さが濃厚で最高だった。
ところが。陽子という女性の登場で物語の方向が一変。突然、熊文学から「人生とは?」みたいな話になっていき謎過ぎるラストを迎える。
私。陽子と同じく出産経験もある女だけど、ラストで陽子が取った行動がまったく理解できなかった。私の理解力が足りないんだろうか? あまりにも唐突過ぎるし「いやいや。他に方法は無かったのかよ?」と真顔でツッコんでしまったもの。
熊爪と言う人物が魅力的だっただけに、ラストは膝カックンを食らわされたような気がしてガッカリ感半端なかった。
河崎秋子が直木賞を取るに値する力のある作家だ…ってことに異論はないけど、どうして『ともぐい』だったのか? 他の作品では駄目だったのか? 直木賞選考委員の馬鹿。もう知らない!