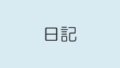身に染みて堪えた作品だった。家族に病人を抱えたことのある人なら、誰だって「うっ」っとくるんじゃないかと思う。
難病を患った姉を持つ大学生の妹の物語で、なんとも、やるせないお話だった。
以下、ネタバレを含むのでご了承のほどを。ネタバレがNGの方は以降は読まないようお願いいたします。
そこにいる人
初めての恋めいた体験に胸をときめかせる大学一年生の直子。だが、彼女には姉・幸恵の存在が重くのしかかっていた。幸恵は肝臓に欠陥があり、長く患っているのだ。
ある時、直子の不注意から姉の病状は悪化し、肝臓移植の必要に迫られる。自分の肝臓を提供すべきなのか、悩む直子がついに決断をした時…。「命」を見つめる感動の物語。
アマゾンより引用
感想
主人公の姉は生まれつき重い肝臓病で、主人公の家族は「お姉ちゃんを生かす」ことを中心にして生活が回っている。
社会に出たことのない姉は病人特有の我がままさがあり、妹は「お姉ちゃんは病気だから」と分かっているのに、心のどこかで不満や恨みを抱えているのだ。
結論から言うと、姉は病状が進んで肝臓移植をするしかなくなり、すったもんだの末、主人公が肝臓の提供を申し出るのだけど、姉は移植手術の前に自殺してしまう……ってオチ。
なんとも、やりきり無いラストだ。
「家族に重い病気の人がいる」って状況になると、どうしたって何某かの犠牲が要求される。経済的にも精神的にも。
家族は「これは仕方ないことだ。家族だから当たり前だ」と心の中では理解していても「どうして私が犠牲にならなくちゃいけないんだろう」と思わずにはいられないものなのだ。
経験のある人なら、誰もが思い当たるのではなかろうか。でもって「そんなこと思ってる自分」に気付くとき、どうしようもなく凹んでしまったりする。
この作品は、そのへんの心の機微が上手く描けていたように思う。
矢口敦子自身、長期闘病経験者だから、ひとつひとつの描写がリアルでたまらない。
ただ、矢口敦子の年齢で女子大生を描くのは難しかったのか、時代錯誤な感じがあったのは残念だった。
いっそ舞台をもう少し古く設定してしまえば良かったのに、携帯電話がある時代とは思えない古臭さが作品全体を覆っていたのは興ざめだった。
矢口敦子は初挑戦の作家さんだけど、機会があれば他の作品も読んでみたいと思う。