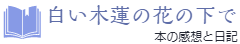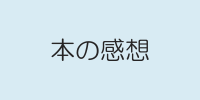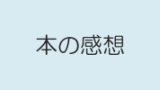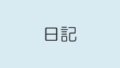『猿の戴冠式』は第170回芥川龍之介賞の候補作。表紙絵が気持ち悪いので今まで手が出なかつたのだけど「言語を学習した猿(ボノボ)」が登場する小説だと知って、俄然読んでみたくなった。
昨年読んだハヤカワSF コンテスト特別賞の『ここはすべての夜明けまえ』とか芥川賞を受賞した『サンショウウオの四十九日』を読んだ時にも思ったのだけど、SFちっくと言うか近未来的な感じの作品ってより先の話」がテーマの作品って最近増えてきているのかな?
このタイプの作品って軽くぶっ飛んだ設定をどこまで受け入れることが出来るか…ってところで感想が変わってくるように思う。
猿の戴冠式
- 主人公、瀬尾しふみは競歩選手のは、ある出来事をきっかけに引きこもり生活を送っていた。
- そんな中、テレビ番組で動物園のボノボ「シネノ」を目にし、しふみはシネノを「おねえちゃん」だと直感する。
- シネノは過去に言語学習の実験を受けたボノボだったた。
- しふみとシネノは独自の手話で心を通わせるのだが…
感想
う~ん。いまいち楽しむことが出来なかった。
猿(ボノボ)のシネノのターンは面白かったのだけど、いかんせん競歩選手しふみのターンが好きにれなかったのが致命的だったのだと思う。たぶん好みの問題。
猿(ボノボ)が思考して一人称で語るのは面白いと思ったし、思考の方向性も良かった。シネノは自分が特別な存在であると考えるているからこそ、テレビニュースのアテレコの声が幼児っぽいとこに怒りを感じているところなどは、なんかこぅ…分かり味があった。
猿と人間の子を同一に語るのはどうかと思うのだけど、私の娘は幼稚園の頃に「小さい子扱い」されることが嫌いだった…と成長してから教えてくれた。子どぽいダンスも恥ずかしくて嫌だったし、発表会の劇で「泣き虫の末っ子ネズミ」の役をするのが耐え難かった…と。
「私を馬鹿にするな!」と言う気持ちって生き物にとって強烈なものだと思う。『猿の戴冠式』は小説でしかないけれど、言葉を持たない動物やあるいは他者と言葉でやり取り出来ない高齢者や障がい者なども「私を馬鹿にするな!」と言う気持ちを抱えているのではないかな…と思ったり。
一方、競歩選手のしふみの思考は個人的に好きになれなかった。一言で言うと「なんだか面倒くさい奴だな」って感じ。彼女の面倒くさい感じが気になる方は自分で戴きたい。本当に面倒くさいので詳細につていは省略させて戴く。
いまいち楽しむことが出来ななかった原因は「しふみが好きになれなかった」ってところが大きいのだけど、もう1つある。現実と妄想の境いが曖昧だった…ってこと。どこからどこまでが現実なのか掴み難かったのだ。ゆっくりと確認しながら再読すれば分かるのかも知れないけれど、再読したいような作品ではない。
「猿が言語を持つ」という設定自体は好きなのだけど、色々とコレジャナイ感じが強かったのと、ほんのり気持ち悪い感じがして苦手な作風だった。でもこれは好みの問題であってレベルの低い小説…って訳じゃないので、あくまでも個人の感想ということでご理解戴きたい所存。